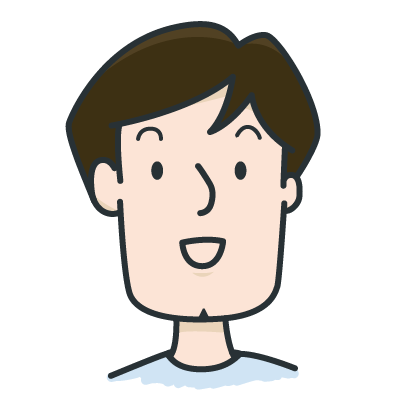
こんにちは!広報デザイナーのyama(@ひとり広報)です
一眼レフカメラは便利ですよね。
写真は綺麗に撮れるしカメラ操作もしやすい。レンズ交換すれば様々なシーンにも対応できます。
綺麗に撮れて嬉しい。だけど、重たいし荷物になる。
というのが、一眼レフへの正直な感想ではないですか?
一眼レフを今は使っていないという方も多いのではないでしょうか。
ボクも長い間、仕事や趣味で一眼レフを使いましたが、本当に一眼レフである必要あるのかな?
と、感じていました。
その後、ボクは一眼レフを手放し、今はコンデジ中心に撮影しています。
一眼レフを手放した理由は、ボクが一眼レフを手放した理由 デザイナー的断捨離 の記事で紹介しています。
今回は、日常的にコンデジを使っているボクがおすすめするコンデジ5機種を紹介します。
個人的なコメントとして、HDR写真を撮る時の良い点も追加しました。
コンデジ推しの理由
小型の一眼レフやミラーレスがあるとは言え「一眼で撮ってます感」はあります。
カメラ本体は小型でもレンズが大きく重いという場合もあり、小型の一眼レフを選んでも結果的にそれなりの荷物となります。
高画質高性能、撮影している雰囲気。
一眼レフの良さであるポイントも「一眼レフを使わない」方にとっては、「重い」「邪魔」という感覚によってスポイルされてしまうわけです。
で、コンデジで撮るのが何がいいかと言えば
- カメラを含めて機材がコンパクト
- 外出先とかでも気軽に撮れる
- 人の中で撮っていても違和感がない、邪魔にならない
- コンデジの画質、処理速度ともに実用上問題ないレベル
いいことばかりなんですが、世の写真愛好家さんは、一眼レフやミラーレスで撮る方が多いですね。
一眼レフに三脚担いで歩くのって辛くないですか?
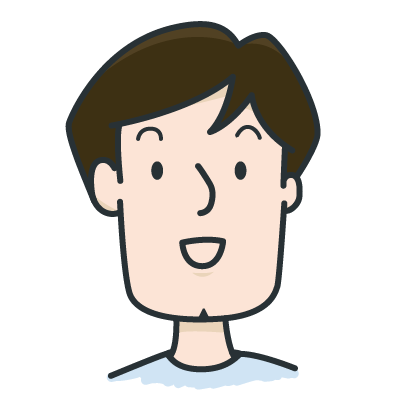
子供たちと行動することが多いので、出来るだけカメラ機材は軽くしたいです。
スポンサーリンク
SONY RX100シリーズ

ポケットサイズの高画質カメラ。初代から超ハイレベルな仕上がり。一番のオススメ!
SONY RX100M4 最もバランスのよいおすすめコンデジ
1インチセンサーの先駆けとして登場したRX100シリーズです。
画質は初代RX100から定評があります。初代RX100とM4を所有しています。
ポケットにも入るほどコンパクトでありながら、基本性能がとても高いデジカメです。
また、レンズの広角端が24mmというのも他機種ではあまり見られない魅力です。
RX100シリーズは製品サイクルが比較的短く、2022年4月現在の最新機種はRX100 M7です。
7世代も発売されているだけあり、非常に完成度の高いカメラです。
SONY RX100M4 のポイント
- F1.8-2.8の明るいレンズ
- 広角24mmスタート(望遠側は70mm)
- ポケットに入るコンパクトなカメラ
- ファンダー装備
- チルト液晶
- 高感度の画質も一般的な感覚では十分なクオリティ
カメラとしての基本性能が高いので、一眼レフユーザーのサブカメラとしてもおすすめです。
タッチパネルは非対応のモデルですが、全体の動作が機敏なので特に不満は感じません。
HDR写真家的にRX100M4の素晴らしい点
RX100M3からAEブラケットが細かく設定できるようになりました。
2.0EVで5ショット、3.0EVで5ショットとブラケット撮影の設定ができます。
また、レンズが広角24mmであることも便利です。
HDR撮影の場合、望遠よりも広角レンズの方が使い勝手良いですから。
個人的には、RX100M3からがオススメです。
RICOH GRシリーズ

スナップ派だけでなく、風景写真を撮る人にもオススメですよ!
ポケットサイズのボディに一眼レフ同等のセンサーを搭載したコンデジ
RICOHの高級コンパクトの代名詞、GRシリーズ。
最新機種はGRⅢ、GRⅢxです。ボクが使用しているのは2世代目のGRⅡです。
GRシリーズはポケットにも入るコンパクトなカメラですが、一眼レフと同等の大きなセンサーを搭載しています。
解像感もバッチリで、風景派の方にもオススメですきます。間違いないカメラです。
スナップカメラとしての性能は折り紙付きです。
特に操作性は抜群です。撮影に使う操作ボタンが右手側に集約しているので、カメラを持ち替えることなく設定を変更することができます。
最新機種のGRⅢ、GRⅢxは手振れ補正もつき使い勝手も向上しています。
RICOH GRⅡ のポイント
- ポケットサイズでも一眼レフ同等のセンサーサイズ!(APS-Cサイズ)
- 操作性の良さはコンデジ界屈指。右手だけで操作できるのは素晴らしいです。
- 手ぶれ補正はないのでその点は注意(GRⅢは手ぶれ補正対応)
- スナップカメラとして魅力的
HDR写真家的にRICOH GRⅡ の素晴らしい点
APS-Cの大型センサーを搭載した「GR」からHDR向けのカメラとなりました。
GRⅡではブラケット幅が2.0EVで3ショット撮影可能。
HDR用としてもブラケット幅が強化されたことで「使える」コンデジとなりました。
ただし、カメラの難点は手ぶれ補正がないこと。
コンデジHDRには手ぶれ補正が必須と考えているので、その点は残念なところです。
スポンサーリンク
SIGMA DPシリーズ

DPシリーズの最大の武器は解像感の高さにあります。FOVEON X3という独自のセンサーによる描写は、コンデジという枠から飛び抜けたレベル。
カメラ背面の液晶の見え方がよろしくないので、撮影時のプレビューでは「こんなもんかな?」ぐらいの写真が、いざPCで開くと「スッゲ!隅々までしっかり描写してる!」ってなります。カルチャーショックですね。
他の機種にない「解像感」が際立つ個性派のコンデジ
DPシリーズの使い勝手をどう考える?
DPシリーズは「描写」は文句なしですが、それ以外は「我慢」が必要。
全体の処理速度が致命的に遅いです。
オートフォーカス、撮影時の書込みなど一般的なコンデジと比較して遅いです。サッと撮ってサクッと確認とはいきません。これをOKと思えない方は、入手してもそのうち手放すでしょうね。
高感度撮影が苦手です。
ボク個人の感想ではISO400まではOK、ISO800では厳しいと感じます。現状のコンデジの中でも高感度での画質は「悪い」部類だと思います。
ですが、丁寧に撮れば素晴らしい画像が手に入る機種です。
DPシリーズを使うHDR写真家が多いのは、その描写に可能性を感じているからでしょう。
SIGMA DPシリーズ のHDR的ポイント
- FOVEON X3による解像感の高さは他のコンデジより頭2つ位抜き出ている
- 3.0EVで3ショットはHDR撮影に充分
- 21mm、28mm、45mm、75mmの画角の違う機種が用意されている
- 基本的な動作がのんびりなので、それを良しとしないと手放すことになる
- dp Quattoroシリーズはカメラが巨大化し、コンデジサイズではない
Panasonic LX5

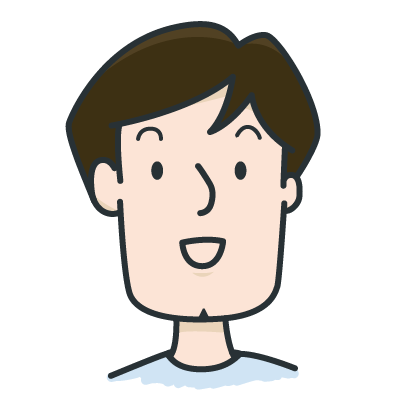
LX5は古いですが大好きなコンデジです!
LX3は2008年、LX5は2010年、LX7は2012年のモデルです。
Panasonic LX5は知る人ぞ知るHDR用コンデジ
2012年頃に中古で購入しました。
LX5の良さは、1/1.7型と小さなセンサーサイズを活かした被写界深度の深さにあります。
元々パンフォーカスになりやすいコンデジですから、f値を抑えて速いシャッター速度でブラケット撮影ができます。テンポ良くサクサク撮影が進められます。
LX5は±3.0EVで3ショットの撮影が可能。また、手ぶれ補正も搭載しているので、コンデジHDRに必要な機能を揃えた当時としては珍しい機種でした。
Panasonic LX5 のHDR的ポイント
- 1/1.7型の小型センサーを活かした被写界深度の深さ
- 3.0EVで3ショットのブラケット撮影(RAW撮影も可能)
スポンサーリンク
富士フイルム X100

富士フイルムの高級コンデジX100シリーズ。
APS-Cサイズの大型センサーとF2.0の明るいレンズ、35mmの標準画角が特徴のカメラです。
見た目はクラシックですが、中身は先進的。特に光学ファインダー(OVF)と電子ビューファインダー(EVF)をミックスしたハイブリッドファインダーが話題になった機種です。
X100のHDRの設定は平凡でも仕上がりは上々
X100の色味はとても自然で、優しい描写をします。
この味はHDR加工しても活きているようで、X100で撮影したHDRは他の機種に比べると優しい「やりすぎていない」HDRになるように感じます。
ブラケット幅は1.0EVで3ショットと平凡ですが、上記の自然な描写から現像されるHDRは他機種とは違った仕上がりになります。
富士フイルム X100 のHDR的ポイント
- APS-Cサイズの大型センサーとF2.0の明るいレンズ
- 1.0EVで3ショットのブラケット撮影は平凡でも、ISOブラケットができる数少ないカメラ
- 高感度の画質の良さ
- 本来の優しい描写がHDR加工しても活きている(気がする)
最後に、今回のまとめ
コンデジらしいコンパクトさ、スマホとは一味違う写真や動画が撮れるという点で一番のおすすめはSONY RX100シリーズです。
RX100シリーズはコンデジの中でも非常に高額なカメラです。
最新機種の場合、10万円以上します。エントリークラスの一眼レフよりも高いです。
RX100シリーズは旧機種も併売されているます。予算に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。初代RX100でも写真画質はとても優秀です。
ボクが実際に使用したコンデジの中でもおすすめの5機種をまとめました。
購入の参考になったら嬉しいです。
それでは、今回はこのへんで。






